「双子の出産って、自然分娩できるの?それとも帝王切開?」「何週くらいで産まれるの?」–私も妊娠中同じような不安でいっぱいでした。
実際、双子妊娠は予定日より早く出産になることが多く、帝王切開になるケースも珍しくありません。
私の場合は、【36週4日】で破水し、予定日の3日前に緊急帝王切開となりました。
この記事では、私が実際に体験した
👉 双子出産のリアルな流れ(破水~手術・退院まで)をまとめています。
これから双子の出産を迎える方の不安が、少しでも軽くなりますように。
最後に、出産前に準備しておいてよかったものや、産後に助かったサポートも紹介しています。
この記事では、私が体験した**双子出産のリアルな流れ(破水~手術・退院まで)**をまとめています。これから出産を迎える方の不安が少しでも軽くなるように、具体的な準備ポイントも紹介します。
- 双子を妊娠していて、出産の流れを知りたい方
- 帝王切開がどんな手術なのか不安な方
- 出産準備をいつ始めたらいいか知りたい方
双子を36週4日で緊急帝王切開!出産の流れと体験談
予定日は37週で帝王切開を予定していましたが、36週4日で突然の破水。
そのまま緊急帝王切開になった私の体験談を紹介します。
出産の流れから術後の痛み、初めての育児で学んだことまで、リアルな経験をまとめました。
深夜2時30分頃、寝ていると、突然水が流れる気配を感じました。
いつも鈍感の私が何かを察して夫を起こしました。「もしかしたら、破水かもしれない」
私が病院に状況の電話している間に夫もすぐに病院に行く準備をしてくれて、スムーズに家を出ることができました。
量は、そこまで多くはなかったのですが、車のシートには念のためバスタオルを敷いておきました。
産院について、車いすで移動させてもらい、すぐに確認して頂きました。
病院につくと、トイレに行ったタイミングでドバっと水があふれて、看護師の方も「破水ですね」と言われ、そのままベッドに横になりました。お腹に機会を装着して、赤ちゃんの様子を見て、「もうすぐ陣痛もくるかもしれないので来る前にこれから緊急帝王切開しましょう。」ということで緊急帝王切開することに決まりました。
私が出産するときは、「コロナ」の時期だったので、PCR検査を2回ほど行いました。もちろん夫は外で待機していました。
コロナの結果が出るまで時間がかかったのか、少し休む時間(30分くらい)がありました。が流れがよくわからず、ドキドキしっぱなしで、休めませんでしたが。
手術室に運ばれるときに夫には会えました。
手術室に入り、色々な準備がスピーディーに行われて、まさに「まな板の上の鯉」状態で、麻酔が打たれ、冷たい保冷剤かなにかを胸元に当てて「感覚ありますか?」と聞かれました。
無事手術が始まり、麻酔で何も感じませんでしたが、声をかけられ「1人目取り上げますね」と声をかけて取り上げてもらい、お腹が波打つ感じでした。手早く二人目も取り上げて同じように痛いという感覚はないですが、波打つ感じでした。
ネットの情報など見すぎていて、「産声がなかったらどうしよう」と不安でしたが、しっかり元気な声で泣いてくれて安心しました。
自然分娩でリラックスした曲を流したりする想像する素敵なバースプランなどではなかったです。手術前に動画などはとお聞きしたら動画は❌だったのですが、スタッフの方がうまくおとり計らいして頂き、出産後すぐ携帯で写真や動画を撮ってくださいました。一緒に双子の誕生を喜んでくれて、うれしかったことを覚えています。
破水が深夜2時30分、帝王切開手術が朝方5時30分、術後しばらくして震えが止まらず、発熱しました。看護師さんも「寒いですか?」と何度も体調を見てくださいました。夜中から起きているのに、目はギンギンにさえていました。
発熱して再度PCR検査しました!
そこから丸1日はベッドで横になり寝ていました。定期的に看護師さんがやってきて、歩く練習が始まりました。
①ベッドの横に立ちあがる練習→この世のものとは思えないほどの激痛でした。
②立ち上がれたら、数歩ずつの練習
③自分でトイレに行ける練習
④赤ちゃんがいる(お世話室の)ところまで歩く練習
痛みが強すぎて、処方された痛み止めを時間を守って飲みました。
傷の痛みもまだ残る中で、いよいよお世話がスタートしました。看護師さんに優しく声をかけていただき、「まずは一人(男の子の方から)をやってみましょう」と、おむつ替えやミルクの作り方を教えてもらいました。
最初はおっかなびっくりでしたが、少しずつ慣れてくると、今度は二人分のお世話。お世話室まで二人を連れて行くだけでもひと苦労で、最初のうちはもたついてばかりでした。
母乳→ミルクの順であげていましたが、胸の張りが強くて激痛…。自分でマッサージすることもできませんでした。壊してしまいそうで怖かったけれど、何事も「慣れ」。二人分のミルクやおむつ替えをこなすうちに、少しずつ要領もつかめていきました。
最初は壊してしまいそうでとても怖かったですが、何事も慣れで、一人で二人分ミルク・おむつと世話をしていくので要領がわかるのも早かったです。
私が入院していた病院は母子同室ではなかったので、3時間おきにお世話室へ通いました。同じタイミングでお世話に来ていたママさんたちと話す時間が、密かな楽しみでもありました。
その中には、私より数日早く出産された双子ママさんもいて、「帝王切開の傷が痛すぎて、私は泣きました」と話してくれたとき、思わず「わかります…!」と共感してしまいました。痛みを共有できる仲間がいるだけで、少し心が軽くなりました。
退院したら、いよいよ自分たちの手で育児をしていかなくてはいけません。
わからないことばかりだったので、入院中はとにかく積極的に質問しました。ときには「動画を撮ってもいいですか?」とお願いし、手順を撮らせていただくことも。
動画や写真を撮る場合は必ず看護師に確認してください。
初めての育児で「赤ちゃんの様子がおかしい」と気づける自信がなく、不安だらけでしたが、聞けるうちにしっかり確認しておいたことは、本当に後から役立ちました。
特に印象に残っているのはこの5つです。
① ミルクの飲む量が少ないときの対処法
② 便秘のときの綿棒浣腸(動画で撮影)
③ 沐浴の手順(両親学級で体験済みでも、実際に自分の子に行うのは別物でした)
④ 公的書類(出生届など)の確認事項・提出時の注意点
⑤ 救急対応が必要なときの赤ちゃんのサイン
※上記に関わらず、自分が不安に思っているところはしっかり質問していければ安心です!
実際の手の動きや赤ちゃんの反応を見ながら教えてもらえたことで、育児書ではわからないリアルな感覚がつかめました。
いよいよ退院の日。
「車で泣かないかな?」「ミルクの時間は大丈夫?」と、家に帰るだけなのに気がかりなことばかりでした。
大学病院だったこともあり、会計にかなり時間がかかってしまい、最終的には本来の退院時間より大幅に遅れることに。
その間は新生児病棟で待たせてもらいましたが、慣れない環境でそわそわしていたのを覚えています。
初めてのチャイルドシートも手際が悪くてなかなかうまくシートベルトをはめられませんでした。
退院最終日の楽しみであったお祝い御前です。
結果的に半分も食べられませんでした。理由としてはお世話の時間がかかって部屋に戻るのが遅くなる、戻っても科の違う先生がひっきりなしに来て、もう慌てて食べました。

出産前に準備・確認しておくべきこと
ようやく会計を終えて、初めてチャイルドシートに双子を乗せた瞬間は「本当に連れて帰るんだ」という実感が込み上げてきました。
出産前にしておいてよかったことは、必要な書類関係に目を通していたことです。
産後は慌ただしく、ゆっくり確認する時間がなかったので、事前に必要な書類をチェックしておいて本当によかったと思いました。
また私の場合、破水したときに夫が一緒にいて車で病院まで行けましたが、もし一人だったら…と後から思いました。
移動手段など、万が一のときの行動を事前に考えておくことも大切だと感じました。
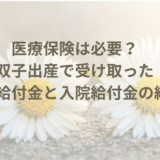 医療保険って必要?双子の帝王切開で21万円もらえた実体験【加入しておいてよかった!】
医療保険って必要?双子の帝王切開で21万円もらえた実体験【加入しておいてよかった!】 想像以上に産後は動けません…。
ベッドから起き上がるのもやっとなので、手元で管理できる工夫がとても役立ちました。
・S字フック
・S字フックにかけられる袋(5枚程度)
→ 書類や薬、ちょっとした小物をまとめてベッド横に吊るせて便利!
・産褥ショーツ・産褥パッド
→ 私は不要と思って準備していませんでしたが、病院で無料でいただけました。
ただし、病院によって異なるので確認しておくと安心です。
・赤ちゃんの退院時の着替え
・自分の着替え(最低限)
面会などで持ってきてもらうにしても、最低限は準備していきましょう。
帝王切開は「予定通り」いくとは限りません。
私も37週での予定帝王切開でしたが、36週4日で破水して緊急帝王切開になりました。
いざという時に慌てないよう、事前に確認しておくと安心です。
・緊急時、1人で病院へ行く場合の移動手段
→ 近隣のタクシー会社に「妊婦でも対応可能か」「どのくらいで到着できるか」確認しておきましょう。
・病室は個室か、相部屋か
→ 私は緊急帝王切開当日に奇跡的に個室が空き、利用できました。
・母子同室か、お世話室でのお世話か
→傷の痛みがあり、移動は大変でしたが、ゆっくり一人になる時間もできたので私は「お世話室通い」でよかったと感じました。
・おむつやおしりふき、タオル類の支給有無
→ サービスとしてもらえる場合もあるので、産院に確認しておきましょう。
・傷跡ケア用品(傷跡テープなど)
→私は途中でやめてしまいましたが、傷跡を軽減したい方は検討してみてもいいかもしれません。
双子のお世話記録をアプリでつけるか、紙(ノート)でつけるかは悩みどころ。
我が家は最終的に「紙派」でした。
理由は、2人分のお世話時間が一目でわかるから。
アプリは便利ですが、1人ずつ記録する形式が多く、混乱しそうだったのでやめました。Twins diaryというノートを購入して記録。
入院中は産院からも記録用紙をもらい、スタッフさんと共有していました。(帰宅後に病院で付けていた記録を映しましたよ!)
退院後、産後ケアで助かったこと
双子を妊娠すると、自治体の保健センターから担当の方がついてくださり、さまざまな相談に乗っていただきました。
その際に「産後ケア」の利用を勧めてもらい、補助もあったおかげで、実際に利用することができました。
産後は体も心も回復途中なので、こうしたサポートを早めに知っておけたのは本当に助かりました。
自治体の補助を利用して、産後ケア施設を活用しました。無料ではありませんが、利用できて本当によかったです。
事前情報で「眠れない」「大変」と聞いていたものの、実際は傷の痛み+双子育児の現実で想像を超える大変さ。
産後ケア施設では、専門スタッフに支えられながら、休みつつお世話を学べる環境が整っていて、体も心も助けられました。
同じ月齢の双子ママさんと同室になり、お友達になることもできました。
この出会いは今後の育児するときの大きな励みになりました。
妊娠中に、まずお住いの自治体のホームページを徹底チェック!思わぬサポート制度がある場合があります。
・ファミサポの割引制度
→ 私の自治体では「2人分の料金を支払いますが申請したら 1人分返金されるという」制度がありました。
・ベビーシッター・一時預かり補助
・タクシー利用券の支給
・産後ケア・訪問支援
育休手当の記事もまとめました。
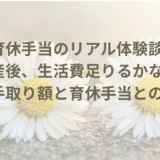 育休手当のリアル体験談|67%・50%支給でもらえる手取りと計算方法
育休手当のリアル体験談|67%・50%支給でもらえる手取りと計算方法 出産レポートまとめ
出産体験談を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
出産は一人ひとり状況が異なりますが、準備できることを少しでも整えておくと、安心感が違います。
大変なことも多いですが、双子の妊婦期間は一生に一度の特別な時間。
どうか無理をせず、自分のペースで楽しみながら過ごしてくださいね。
双子出産は想像以上に慌ただしく、思い通りにいかないことも多いですが、事前の準備とサポート体制があるだけで、ぐっと安心感が増します。
・病院でもらえる入院グッズの内容
・自治体の妊婦・多胎向けサービスの有無
・病院までの移動手段(緊急時のタクシー会社など)
・パートナーの育休時期と、育児・家事の役割分担
・里帰り出産の場合の、転院先・自治体のサポート内容
退院時は荷物が多くなるので、迎えはパートナーや家族にお願いし、車での移動が安心です。新生児期はできるだけ長時間の外出を避けましょう。
・おむつ、ミルクなどの消耗品
※ミルクは病院で使用している種類を聞いておくと安心。合わない場合もあるので、買いすぎ注意!
・出産前後に会社や自治体へ提出する書類(余裕のあるうちに目を通しておく)
・入院グッズは手術予定日の2〜3週間前には準備を始めておくと安心です
双子の出産は、一般的に37週前後で出産になることが多いと言われています。
私のように予定より少し早く破水して緊急帝王切開になることもあります。
だからこそ、「予定通りにいかないかもしれない」という心構えと、少し早めの準備が大切だと感じました。
そして、出産・育児で悩んだときは、一人で抱え込まないこと。
パートナーに言いづらければ病院のスタッフに、制度や手続きで困ったときは自治体に相談を。
声に出すことで、思っている以上に道が開けることがあります。
私の出産レポートが、これから出産を迎える双子ママの不安を少しでも軽くし、
「自分もきっと大丈夫」と思えるきっかけになれば嬉しいです。


