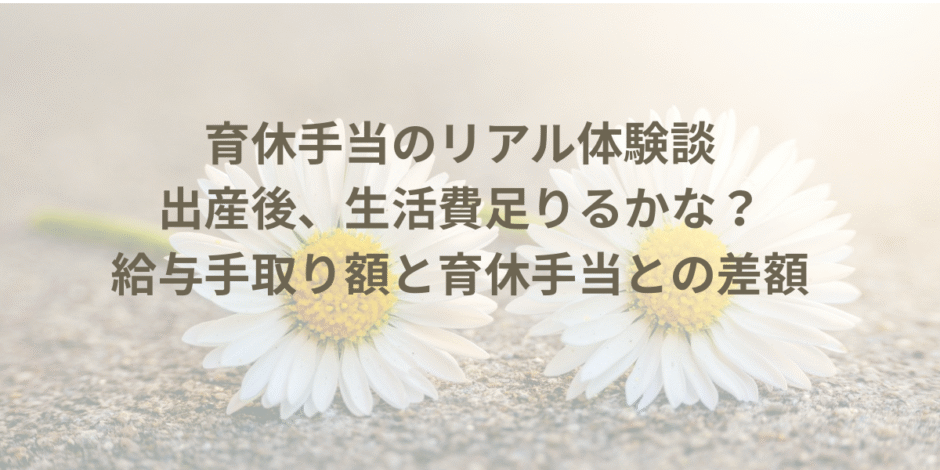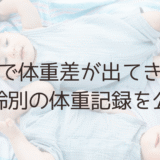※本ページはプロモーションが含まれています
産休・育休に入る前に一番気になったのは「育児休業給付金って実際いくらもらえるの?」ということでした。
結果的に私の場合は、67%支給2か月で349,256円、50%支給になると 2か月で260,640円 が振り込まれました。(2022年8月出産)
この記事を読むと私が実際に受け取った育休手当の金額や、2025年最新制度の手当との差や注意しておきたいポイントがわかります。
これから育休に入る方の参考になれば嬉しいです。
・育休手当、実際いくらもらえるの?
・50%になるのはいつから?
・将来子供のためにいくら残せるか不安な方
1年6カ月の育休期間で貰えた育児休業給付金の合計は2,637,672円でした。内訳は下記になります。
初回の入金日は2022年12月27日(10月17日〜11月16日と11月17日〜12月16日の2回分)に振り込まれました。
| 2022年8月出産 | 支給金額(2か月に1回支給) | 支給率 / 支給日数 |
|---|---|---|
| 10月17日~11月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 11月17日~12月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 12月17日~1月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 1月17日~2月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 2月17日~3月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 3月17日~4月16日 | 174,628円 | 67% / 30日 |
| 4月17日~5月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 5月17日~6月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 6月17日~7月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 7月17日~8月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 8月17日~9月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 9月17日~10月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 10月17日~11月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 11月17日~12月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 12月17日~1月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 1月17日~2月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 2月17日~3月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 3月17日~4月16日 | 130,320円 | 50% / 30日 |
| 4月17日~4月21日 | 26,064円 | 50% / 6日 4月22日より復職の為日割 |
妊娠時期は大変ですが、産休に入る直前の6カ月の給与から算定しますので、つらい時期もありますが、基準金額を下げないように頑張りましょう。
給与:260,000
控除額
健康保険料:12,792円
厚生年金保険料:23,790円
雇用保険:786円
所得税:5,680円
住民税:11,900円
手取り:205,052円
(67%支給と手取り額との差額)△30,424円
(50%支給と手取り額との差額)△74,732円
今年の4月に「育児時短就業給付金」や「出生後休業支援給付金」 が制度として加わりました。
出生後休業支援給付金の制度では、最大28日間は「80%」相当の給付率となっているので、我が家の場合、2025年4月からの制度適用であればどうなったかのシュミレーションをしていきます。
合算(80%相当)
174,000円 + 33,800円 = 約207,800円(産休直前の手取り:205,052円)
ただし「両親ともに14日以上育休を取る」などの条件を満たす必要があります。※細かな条件はしっかり事前に確認しましょう。
厚生労働省/ 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025(令和7)年8月1日改訂版)
育休手当の制度は、年々内容が変わり、正直かなり複雑です。
ネットで調べても情報が断片的で、
「自分の場合はどうなるのか?」までは分からないという方も多いのではないでしょうか。
私自身も、育休手当の金額は計算できていても、
・この先の教育費
・家計全体で見て本当に足りるのか
・保険は今のままで合っているのか
といった部分までは、
自信をもって判断することができませんでした。
そこで、保険や家計のプロに現状を整理してもらい、
「どう考えて、どう決めていけばいいのか」を
一緒に確認することにしました。
結果として、
一緒に確認することで、
先の見通しが立ち、気持ちがかなり楽になりました。
将来のお金が不安な方は、
子どもの教育費が実際どれくらいかかるのかも、
一度確認してみてください。
👉【小学校〜大学までの教育費を試算した記事はこちら】
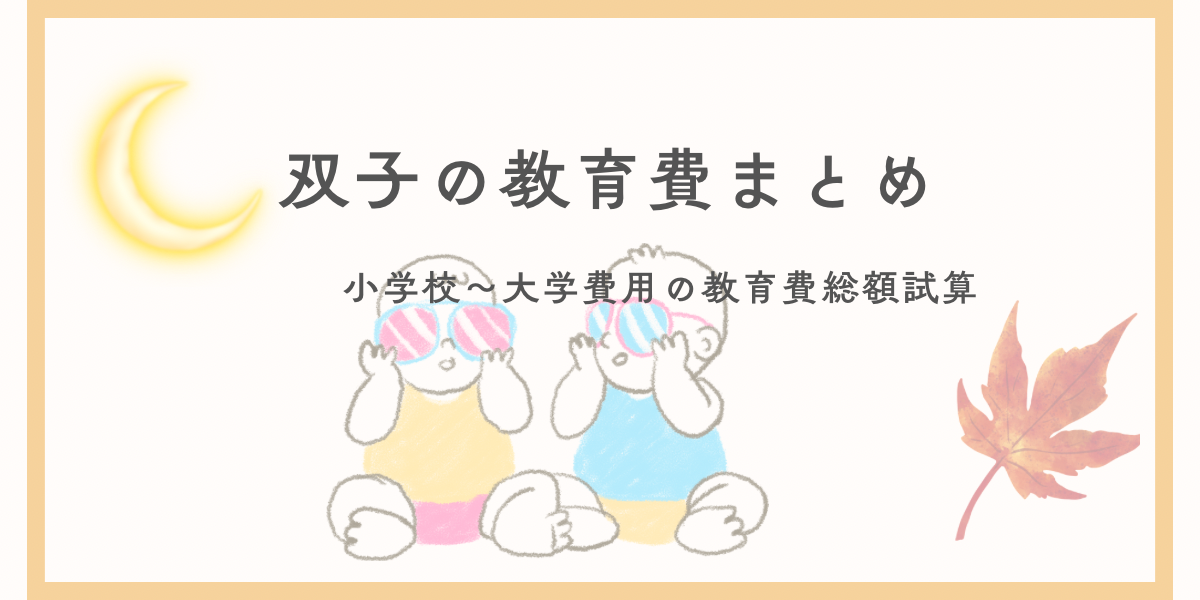 【双子の教育費】どこが一番かかる?小学校〜大学までの総額と“負担が重い時期”まとめ
【双子の教育費】どこが一番かかる?小学校〜大学までの総額と“負担が重い時期”まとめ いかがでしたか。産休手当、育休手当、など我が家も何度もネットで検索してお金のことを少しずつ学んできました。
今では多すぎる情報に調べても我が家に当てはまるのか結果わからないことも多かったので、専門家に細かく相談して、生活費の見直しや保険の加入状況を整理することで、育休後の生活費も安心して計画できました。