「気づいたら、今日も保育園帰ってきて動画ばかり見ている…」
2〜3歳の双子を育てていると、家事や掃除の対応でつい動画に頼ってしまうこと、ありますよね。
「見せすぎかも」「やめさせたいのに泣かれる」と罪悪感を抱くママも多いですが、実は“頼ること”自体が悪いわけではありません。
本記事では、双子ママのリアルな体験をもとに、幼児の動画見すぎにどう向き合うか、無理なく減らしていくための現実的な対策を紹介します。
2〜3歳の時期は「イヤイヤ期」の真っ最中。
一度見たいと言い出したら、動画を消すだけで大泣き…ということも多いですよね。
双子の場合は、片方が泣くともう片方も刺激されて泣き出し、**「泣きの連鎖」**が起きやすいもの。
そのため我が家は「落ち着かせるために少しだけ…」と動画を再生し、そのまま長引いてしまうことも少なくありません。
「見せたくないけど、泣き止まないから見せる」──
この繰り返しが続くうちに、親も子も“動画がないと落ち着かない”状態になってしまうのです。
朝の準備、食事づくり、洗濯、寝かしつけ。
双子育児では、1日のうちで**「どちらか片方を待たせる時間」**がどうしても発生します。
そんな時、動画が少しの間でも静かにしてくれる救世主になることがあります。
頼ってしまうのは、手抜きでも怠けでもなく、「今を回すための現実的な選択」。
特にワンオペの日は、動画があってようやくママが息をつける時間になることも。
まずは、「頼ること=悪いこと」ではないと、自分を責めないことから始めて大丈夫です。
「うちはテレビを見せないようにしてます」
「うちの子は絵本が好きで、動画はほとんど見ないんです」
そんなSNSの投稿を見ると、「うちだけダメなのかな…」と感じてしまうこともありますよね。
でも、家庭環境や子どもの性格、人数、親のサポート体制はまったく違います。
双子育児は、1人育児の2倍どころではない大変さ。
他の家庭と比べるよりも、今の自分たちのペースで「うまく使う方法」を探すことが大切です。
世界保健機関(WHO)や日本小児科学会などでは、
2〜5歳の子どものスクリーンタイム(動画・テレビ・スマホなど)は1日1時間以内が目安とされています。
ただし、これは“理想的な目安”です。
現実には、家事や通院、下の子の世話などでその時間を守るのが難しいことも多いですよね。
大切なのは、「時間の長さ」だけでなくどんな内容を、どんな環境で見ているか。
たとえば、教育的なアニメを一緒に見て話しかける時間は、ただの“見せっぱなし”とは意味が違います。
動画そのものが悪いわけではありませんが、
長時間になりすぎると、いくつか気をつけたい点があります。
- 集中力が続かなくなる(刺激が強すぎて他の遊びに興味が薄れる)
- 睡眠のリズムが乱れる(寝る前の視聴が影響)
- 目の疲れや姿勢の悪化
- ママやパパとの会話時間が減る
とはいえ、これも「1日数時間見せたらすぐ悪影響が出る」というものではありません。
“だらだら視聴”が日常化しないように気をつけることがポイントです。
動画視聴を完全にやめようとすると、子どもだけでなく親もストレスが溜まってしまいます。
特に双子育児では、どちらか一方の機嫌を取るために使う場面も多く、ゼロにすること自体が現実的ではありません。
むしろ、**「使い方をコントロールできるようになる」**ことが大切です。
たとえば、
- 朝の支度が終わったら10分だけ見せる
- 見終わった後に「今日の動画どうだった?」と話す
- 画面を見せる前に「次はおしまいね」と予告しておく
といった工夫を重ねることで、自然と“動画があってもコントロールできる環境”に近づいていきます。
・飽きたら自分で終わりにできます。
・1時間半前後で違う遊びへ移行することがある
・見たいものを自分で選択してiPad操作が自分でできる
・要求通るまで泣き続ける
・声をかけないと自分で終わらせられない
・iPad操作は自分でできず、都度呼ぶ
「動画を見せすぎないようにしたい」と思っても、現実はなかなか難しいもの。
仕事が終わり保育園に迎えにいき、そこから夜ご飯の準備…分刻みのスケジュールの中で、ママ一人の手が足りないのは当たり前です。
だからこそ、“見せ方を工夫する”ことが大切。
ここでは、双子育児のなかで実際に効果を感じた方法を紹介します。
「見せる」と「見せない」の線引きをはっきりしておくと、子どもも親も気持ちがラクになります。
我が家では、
- 朝は見ない
- 夕方の支度時間(17〜18時ごろ)のみOK
とルールを決めました。
ぐずっても「今は見ない時間」と伝えることで、だんだん理解してくれるように。
親側も「今だけ見せよう」と迷わずに済みます。
それでも動画視聴をやめない日もあります。そんな時は、「言葉でちゃんと伝えていく」を心がけています。
うまくいかない日ももちろんありますが、3歳近くなってくると、子供も理解する力がついてきます。「だめなんだ」とわかれば自分で辞める時もあります。
言い続けていくことは大事だと私は考えています。
次から次へと自動再生されると、あっという間に1時間、2時間…。
見せる動画は**“お気に入りの短いもの数本”**に絞るのがポイントです。
ただ見せっぱなしにせず、「さっきの歌かわいかったね」「どんな動物が出てきた?」など、
少し話しかけるだけでも“受け身の時間”が“コミュニケーションの時間”に変わります。
たとえばダンス動画なら一緒に体を動かしたり、工作系なら翌日まねして作ってみるのもおすすめです。
動画の内容を“現実の遊び”に繋げることで、子どもの満足度もぐっと上がります。
気持ちと時間に余裕が産まれた時は双子が楽しんでいるワークブックに取り組んでいます。
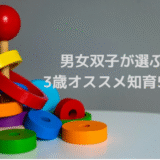 我が家の男女双子が3歳からおうちで取り組むおすすめ知育5選
我が家の男女双子が3歳からおうちで取り組むおすすめ知育5選 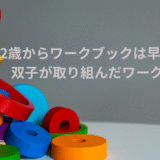 「2歳からワークは早い?」男女双子が実際に取り組んでわかった効果【2歳と3歳の違い】
「2歳からワークは早い?」男女双子が実際に取り組んでわかった効果【2歳と3歳の違い】 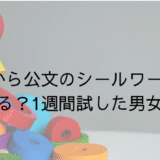 3歳から公文のシールワークは効果ある?1週間やってみた結果、男女双子の反応の違い
3歳から公文のシールワークは効果ある?1週間やってみた結果、男女双子の反応の違い 子どもの発達に悪影響があるのは、**「長時間・受け身で見続ける」**状態。
短時間・目的をもって使う分には、言葉やリズム感を育てるきっかけにもなります。
大切なのは、親が「どんな時に・どんな目的で見せるか」を意識すること。
完璧を目指さず、「今日は助かったな」「この動画、笑顔になれたな」と思えるなら、それで十分です。
また動画を見せてしまった…」
そんなふうに落ち込む日もあると思います。
でも、ママが笑顔でいられることこそ、子どもにとっていちばん大切なこと。
ここでは、罪悪感を少し軽くするための考え方をお伝えします。
動画に頼る時間があるからこそ、ママがごはんを作れたり、洗濯を片づけられたり、少し息をつけたりします。
それは“放棄”ではなく、“家庭を回すための工夫”です。
大人だって、好きな番組や音楽でリフレッシュしますよね。
子どもにとって動画も、そんな「ひと休みの時間」として活用していいんです。
完璧に時間を管理して、毎日穏やかに過ごせるママなんて、そう多くはいません。
大切なのは、“余裕があるように見えること”ではなく、“笑顔でいられること”。
ママの笑顔は、子どもにとって安心そのものです。
たとえ動画の時間が少し長くなっても、「楽しかったね」と笑い合えたなら、それで十分なんです。
「他の家庭はもっとちゃんとしてるのに…」と思うこともあるかもしれません。
でも、双子育児は**“2人分を同時にこなす”**という、まったく別次元の大変さがあります。
「普通」にできない日があるのは当たり前。
だからこそ、他の家庭と比べずに、**“自分たちのペース”**を守ることが大切です。
動画を使うことも、その一つの手段として胸を張っていいんです。
動画をゼロにするより、「どう使うか」を工夫することで、
子どもとの時間も、ママの気持ちもぐっと楽になります。
双子育児は、ひとり育児とは比べられない大変さがあります。
だからこそ、罪悪感よりも「今日もよくやった」と自分を認めてあげましょう。
完璧じゃなくても大丈夫。
“頼りながら笑顔で過ごすこと”が、いちばんの育児のかたちです。
同じ動画を一緒に楽しむこともあれば、それぞれに好みが分かれることもあります。わが家の例です。
この記事が参考になったら、ぜひブックマークやシェアをお願いします📌



